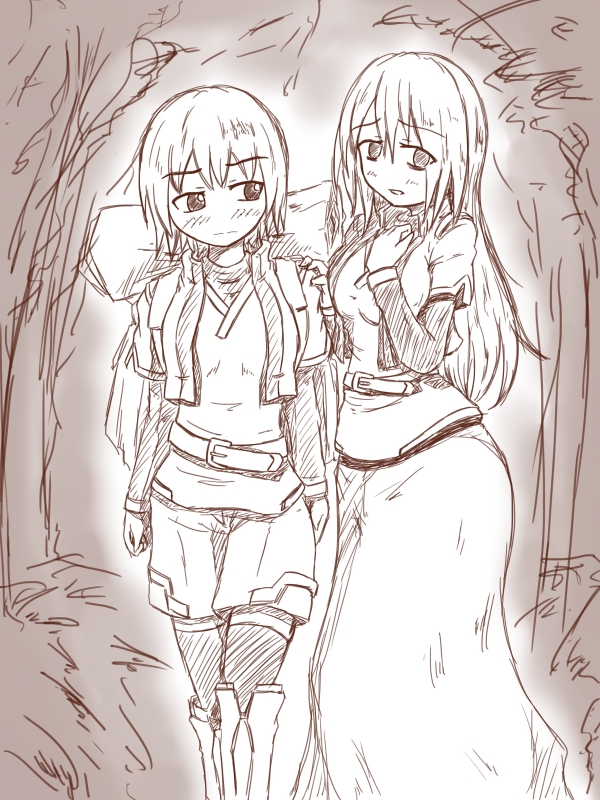――今までどのくらいの獣道を越えて、
「……ほら、お姉ちゃん、もうすぐだよ」
――今までどのくらいの距離を進んだんだろう。
「……まっ……ぁ……」
かなり進んだように感じるときは大概そこまで進んでいなくて、あまり進んでいないと感じるときは実際かなり遠くにいるって、確か昔の賢い人は言っていた気がする。それが正しいとしたら……まだそこまで遠くには行けていないだろう。
足元は少し前までは確かな色を持っていたけど、徐々にそれらが闇と交わり始めて穴も草も同じように見せ始める。そろそろ今日も休む時間かもしれない。
この先に丁度いい場所があるかが分からない以上、安全に移動するためにもここらで一度休憩をとるべきかもしれない。朝方休息をとった場所を片付けたのがもうほんの少し前のように感じられる。これで本当に……人が誰もいない場所にたどり着けるんだろうか……。
「(駄目だ駄目だ!弱気になっちゃ駄目だ!)」
自分に誓ったじゃないか!お姉ちゃんが心安らかに暮らすために、私とお姉ちゃん以外に誰も人間が居ない場所に連れて行こうって!
自分を奮い立たせるようにキッ、と睨みつけた空は、既に夕闇を通り越して幾つもの星々が生命の証を私達に見せつけている。神様は夜の芸術品にどや顔を見せつけてきそうだけれど、今の私はその神様をはり倒してやりたいとすら思っている。
――もしも神が善良なら、どうしてお姉ちゃんをあんな酷い目に遭わせたんですか?
「……はぁ……はぁ……」
肩で息をするお姉ちゃんに、私はここで一晩明かそうと提案する。
お姉ちゃんは……何処までも自信なさそうに、まるで人見知りの子が親の言葉に頷くようにうん、と返事する。縋るような何処か焦点の合わない目、きゅっと私の袖を握る両手の感覚が、私をやるせない気持ちにさせる。昔は力強い瞳で、袖じゃなくて手を持って、私を引っ張っていろいろな場所へ連れて行ってくれたのに……。
ままならない気持ちを抱えたまま、私は山の一画で野営の準備を始めた。お姉ちゃんは手伝わない、ううん、手伝えない。理由は簡単だ。
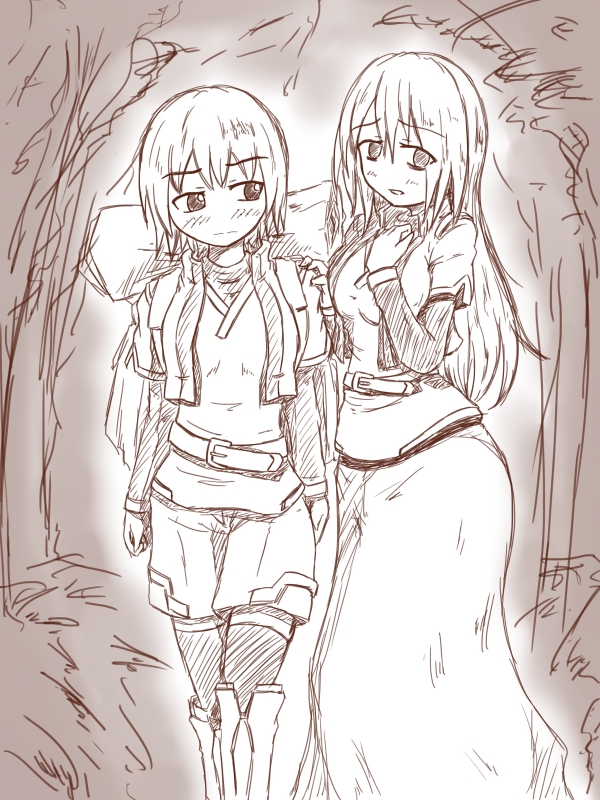
全部、あの事件のせい……。
――――――
昔はお姉ちゃんは、こんな引っ込みがちで、言葉をどもらせ、外では私の背中にずっとしがみついているような人ではなかった。
そうなってしまったのは、忘れもしない二ヶ月前。通い慣れた買い物道の途中で、お姉ちゃんは暴漢に襲われ、連れ去られてしまったのだ。
光の加減によって黄金色にも見える茶とクリームの中間色の長髪に、ソバカス一つない美白顔、瞳は「シスターをやっていたらみんなに安らぎを与えられるんじゃないかい?」と今はもう居ないお父さんとお母さんが言っていたくらい柔和な光を湛え……って、そんな美を讃える典型例がわりかし当てはまる、そんな美人のお姉ちゃんだった。
私?私はお姉ちゃんよりは活発でショートでややミニでナイチチでソバカス有りの自警団員よ。いいもん、私が恵まれたのが美じゃなくて武だっただけだもん。
話を戻して。その暴漢達は前から町で評判になっていた指名手配グループで、自警団員が行方を追っていた。姉ちゃんが誘拐されて気が気でない私を、自警団長は何とか落ち着かせてくれた。
調査の結果、町の廃倉庫にお姉ちゃんが居ることが分かって、体勢を短い時間で整えて、相手の不意を突くようにお姉ちゃんが居る場所の近くからなだれ込んだ私達が見たのは……汚されきったお姉ちゃんであった。
……そこから先は、私はあまり記憶がない。ただ、グループの一人か二人、お姉ちゃんの近くにいた男と女を滅多刺しにした感触だけは、我に返ったときにしっかりと残っていた。周辺に飛び散っていた、よく分からない赤い物体と共に。
町の医者によると、お姉ちゃんは発見されるまでの間、性的も物理的も魔術的にも、どの暴行も受けていたみたい。ボロボロにされた服の下に刻まれた無数の、私が吐きそうになるほどの"証拠"が、何よりそれを物語っていた。
腹や腕、脚に痣、腋や脚には煙草跡、臍と谷間の中間に得体の知れない紋様と切り傷、股間周りに書かれた口に出すのも忌々しい文字……。もう消えることもない、汚されたという証拠。一体、お姉ちゃんが何をしたっていうんだろう、って思えるような仕打ちだった。仕打ちをした人物は今頃は閻魔様の元で裁きを受けていることを祈るしかなかった。
その日以来、お姉ちゃんは人を見ると恐がり、刃物を見ると怯え、火を見ると泣き出して、血を見るとパニックを起こすようになった。……壊れてしまっていた。
日に日に窶れていく、お姉ちゃん。心が壊れきってすり減りきってしまうのも、もう時間の問題と言っても良かったのだ。
――だから私は、他に誰も人が居ないところで暮らそうって、お姉ちゃんを連れ出して、誰も私達を見ていない夜のうちに、お姉ちゃんを連れ出してこの町を出ることにしたのだ。
いろいろな人に向けた手紙を、もう戻らない、でもいつかは戻っていきたいと願う私達の家のドアに貼り付けて。
――――――
食料は、家から相当量、香りのあまりキツくない物を持ってきた。尽かさないように少しずつ、少しずつ大切に食べる食料。それても日に日に背中が軽くなる感覚が、私に危機感を与えてくる。お姉ちゃんは私が食べないと食べてくれないから、私の食事を減らす方法は取れないし、現地での食料調達も限度がある。下手に遠くに行くと、魔物に遭遇する可能性がある。何処か住む場所が見つかって腰を据えてからならいくらでも対応しようがあるけど……今は無理だ。多分、徒党を組んだゴブリンにすら殺されてしまいかねない。
先行きが暗いと、いけない考えが浮かんでしまう……本当に、見つかるんだろうか、お姉ちゃんのために都合の良い理想の環境なんて、私が勝手に外に期待しているだけじゃないのか?
そんなことはない、声を大にして叫べたらどれほど良かっただろうか。でも考えれば考えるほどに、不安が産む暗い思考は私の心を蚕食せんとその触手を広げていく。
「……」
私はちらりとお姉ちゃんを見る。何もかもに怯えきった瞳は、私の近くにいるときだけ緩む。あの日以来変わりきってしまったお姉ちゃん。もう、あの家でそのまま暮らすのは無理もいいところだったと思う。
私の暗い心に問いかけたい。
じゃあどうしろというのか。お姉ちゃんに手をかけろとでも言うのか。
そんな事真っ平御免だ。唯一の家族にそんな事出来るものか!
心の中で不毛な自己対立を起こしつつ、私はただ山の中を、お姉ちゃんと一緒に進んでいく。探して、草を適度に刈りつつ探して……服が私の体に吸い付き始めるくらい空気が湿り始めてきた。空は……まだ曇っていないとはいえ、多分これはすぐに雲が出てくる予兆かな。マズいわね、雨の対策はしているけど、出来れば何処かで雨宿りできる場所が欲しい。
「……アンリ……」
そんなときにお姉ちゃんは私の袖をくいくいと引いてきて、恐る恐る、といった具合に私の横を指さしていた。何があるのか、寧ろ急に何で引いてきたんだろうと片隅で考えつつそちらの方に目を向けると――。
「……こんなところに……」
やっぱり焦りは視野を狭めるわね……。傍目八目とはよく言ったものよ。私はお姉ちゃんに有り難うと一緒に、あそこで休むことを伝えた。
お姉ちゃんは、ただにっこりと頷いた。何処か嬉しそうなその顔は、何故か私よりも稚く見えたのだった……。
―――――――
私達が洞窟の中に入るのを待っていたかのように、空は泣き声をあげ始めた。草木を濡らす音が、埃の香りと共に洞窟の中を幾重にも反響していく。どれだけあるか分からないけれど、それなりの深さはあるみたいだ。中に何がいるか分からないにしろ、今の私達が出来る事はこの洞窟に留まる事だけ。何が悲しいのか、空が泣き止むのは暫く先の事になりそうだ。このまま外に出たら私達が涙も流せない事態になりそうなほどに強く、雨は山を濡らしていく。私はそれに侭ならない思いを抱きながらも、この場所に洞窟があったことが幸運だったと、自分に言い聞かせる事にした。
お姉ちゃんは疲れてしまったのか、それとも張り詰めた緊張の糸が切れたのか、洞窟に入ってすぐ、倒れこむように寝てしまった。今までの慣れない移動に加えて、私以外の人や、それ以外の生き物がいないかずっと気が気でなかったことを考えると、仕方ないのかもしれない。
でも……だとすると、何処に行っても、お姉ちゃんは心休まる事なんてないの……?
もし仮に私以外に誰もいない場所に居たとして、お姉ちゃんは『私以外に誰もいない筈の空間にいる誰か』の事を警戒してしまうだろう。それがいつ治るのかも分からずに……、苦しみ続けてしまうの……?
「……」
一体どうすればいいのか。空よりも泣きたいのはこちらの方だ。でも泣いていても何も解決しない。いつ治るか分からなくても、それでも、私はお姉ちゃんを助けてあげたいと思う。それは私の紛れもない本心だ。
雨はいつかは止む。雲が過ぎ去れば止む。その風に……私はなることは出来るんだろうか……。
「……」
考えていると、私の瞼は気付かないうちに下の瞼とディープキスを交わそうとしてくる。何度でも交わしているのに、よりによってこの時間に交わそうとするのは……もしかしたら、私もまたいつの間にか、体や神経に疲れが溜まっていたのかもしれない。
まだ寝ちゃ駄目だ。せめて、お姉ちゃんに毛布を被せてあげないと……。
――――――
「……」
アンリの姉――メロディが目を覚ましたとき、彼女の妹は地面にうつ伏せになって眠っていた。自分の身体にかかっている毛布が、この妹によってかけられた物であることを彼女は重々理解しているし、そのことについて感謝もしていた。けれど……それよりも何よりも、まず彼女以外の存在に対する恐怖が、彼女の心をずっと圧迫していた。
あの‘事件’によって植えつけられた『恐怖』――ありとあらゆる人間としての尊厳を奪われつくした終わらない無尽蔵の暴力は、ただ一人の肉親である妹、アンリ以外の全ての存在に対してそれを抱かせるようにさせてしまった。
自分を取り囲む、『生き物』が怖い。何かされるんじゃないか、何かさせられてしまうんじゃないか。あらゆる『力』が自分に対して向けられる極限状態から、心はそれに対して防衛するように適応した。いや、してしまった。その結果が……今の、妹の手助けがなければ何も出来なくなってしまった彼女である。
「……っ」
彼女の感情を押し込むように、『恐怖』が大声で喚き続けている。彼女はそれに縛られて、指一本すら美味く動かす事ができない。そんな彼女が妹を縛ってしまっている現状は、彼女の心にさらに過剰な負荷をかけ続ける。
蹲ったまま、彼女は妹の寝顔を眺める。家にいた時よりも、心なしか頬がこけて見えるのは、恐らく気のせいではないだろう。自分のせいだ、自分のせいなのだ。自分が妹に頼りきっているから……。
でも恐怖がそれを妨げる。怖い、怖い、怖い。ただ怖い。無軌道無差別の恐怖が、彼女の体も心も蝕んでいく。耳を塞いでも大声で喚き散らすその声が、何度でも何度でも拳を振り上げ、彼女に不動を、停滞を強いる。
助けを呼べば、妹は来てくれる。でもそのために、妹は自分のことを犠牲にしている。姉として、妹の幸せを願っているのに、それを他ならぬ姉自身が妨害してしまっている。
恐怖に打ち勝つ、それすら侭ならぬほどにメロディの心は衰弱しており、今後回復する見込みが見られるとは思えなかった。もしかしたらいっそ、命を絶てばこの苦しみから解放されるのかもしれないが、その行動すら、恐怖によって阻害されてしまう。袋小路もいいところであった。
侭ならない感情を抱えたまま、未だ降り止まない雨模様の外を眺めていた彼女。その耳に、雨音以外の何かが届く。
「……?」
声、あるいは鳴き声。いずれにせよ意図的に出さないと響く事のない音が、雨音の中を縫うように洞窟の中から聞こえてくる。綺麗な音であった。音と音を繋ぎ合わせていたら歌として聞こえてくるのではないかと思えるほどに。それに、彼女にとっては不思議な事に、その音に対して恐怖を感じることは無かった。
何かに惹かれるように、徐に立ち上がったメロディは、音の方へと足を進めていく。あれだけ締め付けていた恐怖は、ない。一歩、また一歩と、ふらり、ふらり。彼女は洞窟の奥へ奥へと歩んでいった。
次第にハッキリしてくる音。それはどこか懐かしく、どこか温かみのある、心の篭った歌声だった。歌詞も無い、ただラララという歌声だけが印象的な曲。それでも、もっと聞いていたいと思わせる何かが、その歌声にはあった。
彼女の歩みは止まらない。ふらつきながらも、少しずつ、少しずつ奥へ奥へと進んでいく。怖いという思いはない。一欠片も湧いては来ない。湧いてくるものは瞳から溢れ出し、眦から頬を伝うものだけ……。
ぼやけた視界の先……巨大な洞窟内の湖の中に、彼女は歌の主を見つけ――。
――――――
「……んん……」
土の香りがする。耳に響くのは依然として外で激しく降る雨の音。まだこの洞窟で過ごさなければいけないことに歯がゆさを覚えた私が、身体の温かさに引きずられる眠気にさよならを告げてゆっくりと目を開く。お姉ちゃんはきっとまだ眠っているだろう。本当だったら、洞窟の内側や外側からの魔物の来襲に備えて、警戒していなければいけなかったんだけど、思ったよりも身体は疲れを溜め込んでいたらしい。
そうして目を開き、ぼやけた視界がピントを取り戻していき……!?
「お姉ちゃん!?」
居ない!お姉ちゃんが居ない!被せていた毛布は私の体にかけられていたってことはもう起きているって事で……でもお姉ちゃんは自分ひとりでどこかに行くなんて事が今は出来ない筈!
混乱と焦りから、私の背中に冷たい汗が走る。もしかして、魔物にさらわれた!?でも、どうしてお姉ちゃんだけを!?嫌な予感が私の頭の中を巡る。いけないいけない。勢い任せで出て行ったら助けられなくなる!
まずは私の周りを確認しよう。もしも魔物が来たならばそもそも足跡やその手の痕跡があるはず……見当たらない。代わりに、お姉ちゃんの足跡らしいものが、洞窟の奥へと点々と刻まれていた。ここに私たち以外に入ってきた形跡は無いから、間違いない。お姉ちゃんは洞窟の奥にいる!
「お姉ちゃん!」
護身用のナイフ及び探索用のカンテラを手にとって、私は洞窟の奥へと歩いていく。心なしか早歩き気味で。
少しずつ、空気が湿ってきている。それどころか、洞窟の壁面や地面がどこかぬめりを帯びているようにすら感じられる。スライムの生息地かもしれない。油の補充をしておくべきだった、と自分の不注意さを反省しつつ、いざ襲われたときにはこれだけが頼りになる、とカンテラの取っ手を強く握り締めた。
「……」
視線を感じる。何かに見られている。罠なんだろうか、それとも私を警戒しているんだろうか。それはわからないけれど、気にしてはいられない。今はお姉ちゃんを探す事が大切だ。
「お姉ちゃーーーん!!!」
大声で呼んでみる。もしかしたら声が届くかもしれない。返事してくれるかは分からないにしろ、叫ばなければいけないのだ。黙っているときよりも、見つかる確率が高くなるならば……!?
「『――んぁ、ぁぁああ〜〜〜っ!!!』」
「!?お姉ちゃん!?」
洞窟の奥から、お姉ちゃんの叫び声が聞こえてきた!何をされているのかは分からないけど、ただ事ではない事態になっているのは間違いない!早く助けなきゃ!!
私はナイフとカンテラを握り締め、洞窟の奥へと駆けていった。
洞窟は基本一本道で、ただ奥が深かっただけのようだった。ただひたすらに一本道を走っていく私。時間の感覚が分からない。カンテラの光が無ければ見えないような空間で、私は両足を懸命に動かしていた。
道中何度も躓きそうになりながらも必死に進んでいく私の耳には、さっき響いたお姉ちゃんの声が何度もリフレインしている。無事であって欲しい。先程まで憎たらしいとすら思っていた神様に祈りを捧げながら、ただ洞窟の奥に、湿気が先程よりも強くなった奥へと脇目も振らず両脚を駆動させていく。
視界の先、壁に青く光る魔晶石がぽつぽつと埋め込まれた地帯の奥。そこには地底湖があった。地下水が湧き出た、山の空洞地帯。天井に生えているだろう魔晶石から降り注ぐ柔らかな光があるからか、その周囲に緑色が見える。植物が生えているらしい。
「……!?」
人影……らしきものが見える。どこか蹲っているようにも見えるけど……何かがおかしい。地底湖に近付くにつれてその違和感は確信へと変わり――衝撃へと変化した。

「……ぁー……」
「ふふ、ゆっくり……お休みなさい♪辛い事も悲しい事も、全部ママの中に吐き出しちゃっていいのよ♪」
――スライムマザー。
自警団員の一人から聞いたことがある、SSクラスの魔物だ。外観はスライムのドレスを纏った人間の女性という表現が正しい。人間における臍に当る部分がコアで、そこが弱点だって話がある。人里を訪れたとしても人間を襲う事はないが、退治しに来た冒険者達や迷い込んだ旅人を襲う事はある。行動原理は分からない。人間を食べるとか子供にするとか色々と噂だけが一人歩きして、正しい情報は何一つ分からないのだ。
色素が薄い、光によっては真っ白に見えてしまうような肌理細やかな肌を惜しげもなく晒し、私の位置からすれば見せ付けるようにだらしなく股を開いている。その股の間から――どこか解放された様なぼうっとした表情の、お姉ちゃんが――お姉ちゃん!
「お姉ちゃん!!??」
今まさに、スライムマザーがお姉ちゃんを襲っている!反撃する気力もないくらいにとろとろになったお姉ちゃんを、スライムマザーは人間ではありえないくらいにお腹を膨張させながら呑み込んでいく!何とかして助け出さなきゃ!
左手にカンテラを、右手にナイフを構え、私は吶喊した。例え相手がSS級であっても、お姉ちゃんを助けるためだったら私は死んでも構わない!あの事件の日にそう自分に誓ったもの!!覚悟しなさい!スライムマザー!
自分を奮い立たせながら、私は、狙いをつけるためにスライムマザーを見て……。
「……ふふ……♪」
「……え……?」
……見て、しまった。
喜びも悲しみも全てを受け入れる寛容さを。
春の陽だまりのような優しさを。
時に厳しくなれる芯の強さを。
そして、娘のためなら自ら傷つく事も厭わない、純粋な愛情を……。
それら全てが詰まった笑顔は、私の心から戦意という戦意を、敵意を奪いつくしてしまった。あれだけ誓った決意すら跳ね除けて、私の心は彼女への敵意の刃を納めてしまった。じぐじぐと、心が涙を流し始める。理由は分からない。けど、スライムマザーの笑顔を見たとき、まるで彼女を母親のように感じてしまったのだ。親や家族に刃を向けることが出来ないように、彼女にもまた、刃を向けることを心が抵抗し、拒否していく……。
お姉ちゃんを助けなきゃいけない、それは分かっているんだ。でも……。
「……あー……♪」
……こんなに、お姉ちゃんが幸せそうな顔をしていて……。
身体は動かなくて、今にも呑み込まれようとしているのに、心の底からそれを喜んでいて……。
もし奪ってしまったら、この笑顔が無くなっちゃうんじゃないかって思えて……。
「……」
私の手から、ナイフとカンテラが滑り落ちて、地面にぶつかりそうになる。それをスライムマザーは自身のスライムの身体を伸ばして、柔らかく受け止めると、そのまま草の無い、地面が掘り下げられている隅の場所へと置いていった。そしておいで、と両腕を胸の前に広げつつ、私の体を、まるで背中へと手を合わして抱き締めるようにスライムを使って招き寄せてきた。
抵抗する事なんて出来なかった。元来ひんやりしている筈のスライムのはずなのに、どこかぬっとりとしたその身体は、身体の芯から暖めていくような、そんな優しく柔らかな熱を感じた。熱に浮かされる心地に委ねるように、私は一歩一歩、スライムマザーに向けて足を進めていった……。
段々と、お姉ちゃんの声が遠くなっていく……ずる、くぷ、ずるる、くっぷ……スライムマザーの中に呑み込まれているんだ……。どうにかしなきゃいけない。そんな思いが、私の中から私に向かって叫び声をあげる。けど、身体はそれに逆らうように、時間をかけて、ゆっくりとスライムマザーに向かって歩いていくだけ……いや、ゆっくりになっているのは、私の心が身体に抗っているからだ。もしも心も身体も一緒の思いだったなら、既に走り出していただろうから……。
――ぽふん。
永遠のように思える時間をかけて、私が辿り着いたのは、スライムマザーの胸の中だった。人間の胸の中に顔を入れたことがないし、そんな機会もそうするつもりも未だ嘗てなかったけれども、それでも人間のそれとは違って、何処か弾力的なものを感じてしまう。まるで肉の代わりにジェルかその辺りの物体が入っているようだ。それでいて、何処か暖かい。このまま眠りに落ちてしまいそうなくらい、暖かくて、柔らかくて……。
……とくん
「……?」
ふと、スライムマザーの首元が少し震えたような気がした。なんだろうと、ぼやけた視線を上に向けてみると、丁度私の目と鼻の先に、紅くて小さな球状のものが見えた。それは時折、まるで私達の心臓が脈打つようにとくん、とくんと震えている。多分、これがスライムマザーの本当の核なんだ。
――もしかして、これを握り潰せば、お姉ちゃんは――
「――!?っっ!?」
頭の片隅に浮かんだその考えに悲鳴を上げるように、私の心は痛みすら感じてしまうような恐怖を覚えた。コアを潰す事、それは今私をゆっくりと抱き締めてくれているスライムマザーを殺してしまうということに他ならない。温もりも、優しさも、愛情も全てふいにしてしまうのだ。そんなこと……そんなこと……っ!!
知らず、身体はがたがたと震えてしまう。お姉ちゃんがいなくなってしまったらと考えたときよりも、もっと激しく、心がその考えを拒絶していく。寒い。まるで木枯らしが身体を貫いていったかのように、心が寒い。
「あ……ああ……!」
身体に力が入らない。動く事すら出来ない。ただただ、そんな事を考えてしまった自分が怖い、怖い、ただ怖い。
お母さんとお父さんが亡くなったあの日のことを思い出してしまう。もう会えないと分かったとき、もう目を覚ます事もないと分かったときの、言葉に表しようのない喪失感。目頭に熱いものが溜まって、流れ落ちていく感覚……あの時と同じ感情が、いや、それをさらに増幅したような感情が私の頭を、身体を満たして、収まりきらなくなって、涙としてあふれ出していく……!
「ああ、あ、あ、ああ、あああああああああああああああああっ!!」
感情の奔流に耐えられなくなった私は、スライムマザーの胸に頭を押し付けて、叫ぶように泣いていた。泣いても泣いても、悲しみと恐怖は決壊したダムから溢れ出す水のように私の感情を四方に暴れ周り、色を染めていく……。お姉ちゃんのことを考える事すら出来ない、そんな余裕なんて無い。自分の思いが、自分の思いを押し流している……!
「ごめんなさい!ごめんなさいぃっ!ごめんなさいぃぃぃぃぃぃぃっ!」
怖くて、死を願う事を考えてしまった自分が怖くて、そこから逃げ出したくて、逃げ出してしまいたくて私は何度も、何度も、泣きじゃくりながら謝っていた。他の誰にでもない、スライムマザーに対して。それがおかしいと思うことなんて出来なかった。おかしかったら、何で私はこんなにも悲しいのだろう。何で私はこんなにも怖いんだろう。失ってしまう、喪ってしまう。それがどれだけの悲哀と苦痛をもたらすか、私は分かっていた筈なのに、どうしてそれを自ら選ぼうとしてしまったのだろう……!
だんだんと、声が枯れていくのが分かる。それでも私は、謝る事を止めることは出来なかった。ずっと、心の中のもやもやしたものを吐き出してしまうかのように、私はずっと謝っていて……。
ぽふん
「――っ!?!?」
私の後頭部辺りに、何かが触れる。それも暴力的な衝撃ではなくて、もっとこう、赤ちゃんの背を擦るときのお母さんの手のような緩慢な触感が私に伝わってくる……一回、二回、三回。一定のリズムで、私の頭を撫でるように触れては離れる事を繰り返している……。
滲んだ視界の中でスライムマザーの腕が、私の背後に伸びている。とするとこれは……スライムマザーが私のことを……?そのまま視線を上にすると、そこには眦を下げた、溢れんばかりの微笑を称えたスライムマザーの顔があった。
「よしよし……いい子……いい子……♪」
まるで我が子に語りかけるような柔らかな響きを持った彼女の声は、恐怖に冷え切って震えている私の心に、春の訪れを告げさせる温かく優しい風を吹き込んでいった。その間も、彼女は私を撫でることを止めることは無かった。私がまるで、赤ちゃんみたいだ。
「ひぐっ……えぐっ……いぐっ……ごめ……な……ざ……」
赤ちゃん、というよりもまるで私がスライムマザーの子供になってしまったかのようだった。イケナイことをして、お母さんが悲しんでしまうような事を言ってしまって、それを涙ながらに謝っている。そんな、遥か昔に通った道を、今此処で繰り返してしまっている……多分、頭が回っていたら、私はそんなことを考えていたに違いない。けれど……悲しみも怖い感情も、声や涙と共に吐き出していた私には、そんな余裕も思考もなかった。
「いいのよ……貴女も一生懸命だったんでしょう?メロディちゃんを助けてあげたくて、幸せにしてあげたくて……♪」
だから、と続けたスライムマザーの顔に、何処か決意にも似た色が浮かんだ……みたいだけど、私はただ泣きじゃくるだけで、視界も滲んでいたし、分からなかった。ただ……私を強く抱き締めながら彼女が語りかけた言葉は、私の悲しみを、恐怖を吹き飛ばすほどに力強く、暖かく感じられた。
「だから、いいのよ。私はメロディちゃんも、貴女のことも、全て受け入れるわ。そして……二人とも幸せにしてあげる♪
それが、母としてのつとめだもの♪」
彼女の纏うスライムドレス、その胸に掛かっている部分がどろり、と崩れ、白磁の肌にぷくん、と膨れた桃色の突起が現れた。その突起の先端は肌の張りの強さも合わせて主張するようにピン、とやや上気味に立っている。
「さぁ、声もがらがらでしょ?私のお乳をおあがりなさい……あんっ♪」
差し出された乳首に、私の体は自然に反応し、そのまま口に含んでいた。ちう、ちう、ちう。傷つけないように、でも中から少しずつ搾り出すように、私は乳房をしゃぶりつつ、乳首をちろちろと舐め、彼女の乳に吸い付いていた。自分で何をやっているのか、自分でも分からない。ただ、「おあがり」と言われた時には、私の体は勝手に動いていた。
「んっ……んん……♪」
お乳を吸われていることが気持ちいいのか、スライムマザーは口の中に収まりきらない喘ぎを漏らす。表情は当然見ることは出来ないけれど、声からは嫌そうな感じは見られない……嬉しそうだ。私の首の辺りから、髪の毛をさわさわと触れるように、彼女の手が優しく撫でていく。それだけなのに、何処かくすぐったくて、でも暖かくて……気持ちよかった。
ぷぴゅ、という音と一緒に、スライムマザーのお乳から何かが飛び出す。それは優しい甘みとぷるぷる震える弾力性を持ったもので……次々と口の中に入っては、喉の奥へと消えていく。きっとこれが、スライムマザーのお乳……。
「んっ……んちゅ……ん……ゅぱ……」
「んぅ……ふふ……お腹が、空いていたのね……♪」
足りなかったものを満たすように、私はスライムマザーの乳に吸い付いて、お乳を与えられるままにこくこくと飲んでいた。お腹の中に、スライムの乳が溜まっていくのがわかる。お腹が一杯になっていって、頭の中がさらにぼうっとしていく……。
ふとそのまま上に視線を向けると、スライムマザーの顔が、私に近付いていた。それはとっても自然で、だから頭がふわふわした私は何も構えることも出来なくて……。
「――ちゅっ♪」
――あ……キス、された……。まるでスライムみたいにふるふるしているけど、私の唇にぴっちりくっついて、まるで唇自体がキスされているみたい……。唇同士が触れ合ったのは一瞬だったけど、私にはその時間が山登りしてきた時間よりも長く感じられた。
ちょっと悪戯っぽく微笑んだスライムマザーに、私はすこしむぅ、としかめっ面を向けてしまう。どうしてすぐやめてしまったのか……もっとして欲しかったのに。どうしてそんな事を思ってしまったのか、疑問にも思わなかった。理性は夢の中、今此処にあるのは、安堵と、求める心だけ……。
「うふふ……、もっと、して欲しかったのかな〜?」
当たり前だ、とばかりに私は首を縦に振る。もっと気持ちよくなりたい。もっと、もっと……スライムマザーと触れ合っていたい。スライムマザーの手が私の体に触れるだけで、スライムマザーの身体にこうして抱きついているだけで、こんなにもあったかくて、優しくて、気持ちいいんだもの……。
「――んぷっ!!」
もっと、とおねだりしようと開かれた口を塞ぐように、スライムマザーは自分の唇を接触させてきて、そのまま舌まで私の中に伸ばしてきた!私の中に突然入ってきたその感触に初めは驚いたけど……まるで隅々まで丁寧にお掃除をするようにゆっくりと動いていくスライムマザーの舌が、歯茎から歯間から舐め擽っていく度に、触れられた場所からじんじんするような不思議な感覚が広がっていって……おねだりするようにいつの間にか私も舌を伸ばしていた。
「んん……んちゅ……くちゅ……ちゅ……♪」
私の拙い舌の動きをエスコートするように、スライムマザーの舌は私のそれと絡み合いながら、時に締め付け、時に寄り合って、ぬっとりと唾液に似た何かで私の口の中を満たしていく。二匹の蛞蝓はスライムの洞窟と化しつつある私の口内で淫靡とも思えるダンスを踊っている。その間にも私の口内のあらゆる粘膜はスライムマザーのそれへと塗り替えられていくのが分かる。触れられた場所からじんじんと、私の中にもどかしいような切ないような、それでいて暖かくて満たされるような疼きが広がっていく。時折スライムマザーが私の口の中から唾液や汚れを吸い込んでいく度に、私がお口の中から綺麗にされていくようで、それだけじゃなくて私がスライムマザーの色に全て染められていくようで……。
スライムマザーによって与えられた彼女の唾液は、そのまま喉の奥へと滑り込んで……プルプルとした質感を持っていく。それが嚥下されていく度に食道も、その先も、全て綺麗にしていくような気がした。スライムマザーは、もしかしたら私を体の中からきれいきれいしているのかもしれない……そんな気さえした。
マザーとのキスは終わらない。私がじゃれ付くように差し出し絡み付けた舌を、彼女の下はその上からさらに包み込んでいく。それだけじゃなくて、私が舌を離そうとしたら、何処か名残惜しそうに舌の腹の辺りを愛撫し、裏筋を舐め擽ったりして……。
「……っは……ぁ……♪」
つ……と、二人の間に唾液の橋が掛かるのを眺めつつ、スライムマザーは笑顔で唇を私から離していった。二人の間に掛かっていたそれは、重力に従うように、私達の胸が重なる辺りへとゆっくりと落下していく……。服が見えないのは、多分スライムマザーが脱がしたからだ。私としても、それでよかった。だって、もっとスライムマザーを感じていられるもの……♪
「うふふ……♪」
まだぼうっとしている私の背中を優しく擦りながら、スライムマザーは私を再びゆっくりと抱き寄せていく。背中から、お腹から、産まれたままの体になった私の全身にマザーのスライムが被せられていく。じわじわと皮膚を、私を包んでいくそのぬるぬるした柔らかな感触が、何となく優しくて、気持ちよくて……暖かくて、嬉しかった。もっと、もっと包まれたい、そんな願いを叶えてくれるように、スライムはじわりじわりと上がっていって……首から下はもう全部覆われてしまった。
「ふふ♪いい笑顔ね♪女の子は笑顔が素敵なのが一番。お母さんはそう思うわ♪えぇと……」
……そうだ、まだスライムマザーに私の名前を言っていなかった。何で言うのを忘れていたんだろう。
「……アンリ、です」
「ありがとう、アンリちゃん♪でも、そんな他人行儀な口調で話しかけられたら、お母さんは悲しいわ……」
悲しい、その言葉だけで、私の心はちくりと痛んでしまう。なんで自分から離れてしまうような言葉をスライムマザーに使っていたのだろう。そんなことしなくてもいいのに……。
「……ごめんなさ――ふぁっ♪」
謝ろうと動いた口は、突然 蠢きだしたスライムによって言葉の行き着く先を変えられてしまった。まるで絹で出来た指が背筋を弦にして爪弾いているような優しい感触が、私の胸を高鳴らせていく……。
「ふふ♪まぁそれは、ゆっくり……ゆっくり慣れていけばいいものだから……私とアンリちゃんの心の距離、ゆっくり……埋めていきましょう♪」
まるで竪琴を弾くように、マザーのスライムが私のせなかをゆっくりと這い回っていく。優しい、それでも何処か力強い愛撫に、私はただ声にならない喘ぎ声を上げるだけだった。
ふわり、ふわり。マザーの身体から、何かがゆらゆらと立ち昇っているような気がした。それはふわふわと私の体の周囲を回りながら、すっ、と口から鼻から、空気のように私の中へと入っていく……柔らかくて、甘い。例えるならべとつかない綿菓子のような、舌先からすっと体の中に広がっていくような甘さ、そんな素敵な香りが、マザーの中から発散されている……。
思わずぎゅう、とスライムマザーの身体を抱き締めて、身体の香りをすんすんと嗅いでしまっていた。密着すると香りだけでなく、マザーの持つ暖かな熱も伝わってきて……撫でられている背中の何処かくすぐったい感触もあって、声をマザーの身体に押し付けながら私の体はびくびくと震えてしまう。
マザーのスライムは、私の背筋に沿って、首筋から尾カ嚶怩フあたりまでの肩甲骨から背骨が描くラインを、ゆっくりと撫で擽っている。時折マッサージを思わせるような動きで私の背筋を揉み、皮膚の下に隠された性感帯を刺激したり、吸い付いて、キスの雨を降らしていく……。その一連の動き全てに、私の心臓はどきどきと激しく反応して動いていた。
マザーの脈が、私に伝わってくる。マザーだけじゃない。マザーの中にいるお姉ちゃんの脈も、わたしの体の中に伝わってくる。とくん、どくん。その響きに合わせて打ってくれない私の脈がもどかしい……一緒になれたら、きっともっと気持ちいのに……?
「――んむぅ!?」
もどかしさを覚えた私の胸が、突然ぐにゃりと形を変化させ始める!私の胸にもそんなに動く余地があったんだ、と思えてしまうほどに、皺寄せられ、凹ませられ、揉まれていく。それだけじゃない。
「――んひぃっ!ひん、んぅ、ぅんんんんっ!!」
乳首!私の胸の中で唯一自己主張をしていると思われる乳首が、マザーの手によって直に弄られている!
「うふふ〜♪可愛らしいお胸ね♪知っているかしら?小さいお胸を持つ子はね……いーっぱい幸せにしてあげる事が出来るのよ♪」
幸せにしてあげる……そのマザーの言葉だけで私の胸はさらに高鳴り、乳首の隆起がさらに止まらなくなる!ぷくりと幽かに膨れた私の乳首を、スライムと連動するように寄せてあげた胸と共につまみ、擦り、軽くねじり、乳の出口をぷにぷにと触れ……そしてスライムが吸い付いていく!
「ひぁ、んぁ、あぁ、ああぁ、ぁぁぁぁあああんんんんんんんっ!!??」
痛みとはまた違う、ピリピリするような刺激が、私の胸からじわりじわりと体の中に広がっていく!もどかしいような、もう少しやって欲しいような、複雑でどっちつかずな感情に私は思わず股間をもじもじとさせてしまっていた。その間にも私の両胸はゆっくりと揉まれながら吸い付かれて、背中には愛撫とキスの雨が降り注いでいて……その動きは、徐々に下へ下へと広がっていって……。
「そろそろ……いいかしら……♪」
「……?」
なにが……いいのだろう……。スライムマザーの言葉に私の心の片隅が?マークを浮かべた、その次の瞬間だった。
「……?……??」
その刺激を、私の頭は一瞬理解できなかった。ただ、何だろう。足の力が、脚の力が、腰の力が、背中の力やお腹の力、腕の力、肩の力、その他諸々の力が一気に抜けていって、抵抗する気力すらも保たせる気力すらも一気に抜けていく、この異様な感覚は。その震源地が、理解できない。いや、理解する力すら、抜けてしまったのかもしれない。
今の私の頭は、目の前に迫る大津波を前に為す術もなく固まっているような状態だ。後は流され、溺れてしまう。それが分かっているのに、前も後ろもなく、ただ立ち止まってしまっているだけの状態。
津波の名前は本来私は理解していた。けれど今、それに溺れてしまったら私がどうなるのかも分からず、ただ前に迫る津波の名前すら、頭の片隅にすら浮かばない。……私の名前すら、浮かばない。
真っ白だ。真っ白に染まっていく。マザーの中で、ま、っ、し、ろ、に……!
「――!!!!!!!!!!!!!!!!」
――ぷしゃぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ……。
……声にすら、ならなかった。背筋を伝って、胸を弄られて昂ぶらされてきた私の心は、不浄の御門とも呼ばれる場所へと指をつい、と押し込まれた瞬間に決壊した。全身から力が抜け、尿道から溜まった尿が押し出され、流されてはマザーの身体を汚していく――前にスライムのスーツに吸収されていく。同時に、お尻からも何かぬるりと出て行ったが……それは尿の吸収よりも早くスライムの中にすぐに融合したみたいだ。妙に、体の中が寂しい……というより、軽い。軽いけれど……どうしてそうなったのか、今の私には理解できなかった。
溢れたのはそれだけではない。秘所自体からも、何か粘っこい液体のような何かが溢れ、身体を覆うスライムへと浴びせていく。逝った。もしかしたらこれが、あのお姉さんを苦しめた奴らが言っていた「逝く」という状況なのかもしれない。
全身の震えが止まらない。寒い環境の中にいた時よりも激しくわたしの体は震えている。それなのに、それなのに何でこんなにもあったかいのだろう。何でこんなにも――気持ちいいのだろう。
あぁ、駄目だ、なにも、考えられ、ない……。

「……うふふ♪アンリちゃん、気持ちよかった……?」
ぼんやりとした視界の中で、笑顔で私を抱き締めつつ胸を差し出し、くわえさせているスライムマザーの姿が見える。私はぼんやりとマザーを見つめながら、こくこくとマザーのお乳を口にしていた。甘くて美味しいマザーのお乳。それに、咥えているだけで、何となく安心してしまう……。
そんな私の頭を、スライムマザーは優しくさすさすしてくれる。まるで私が、スライムマザーの赤ん坊になってしまったみたいだ。そしてそれもいいかな、なんて思えてしまう。
ふわり。マザーの身体から柔らかな香りが立ち昇り、私の体を包み込んでいく。あったかくて柔らかな香りが、私の心をとろとろにしていく。とろとろ、まるでスライムみたいに。
「ふふ……どんどんおあがり♪」
どんどん、という言葉通り、スライムマザーのお乳がお腹に溜まっていく。今度は急に離される事はなかった。お腹一杯になるまで飲んだ私の口は、乳首を離すと同時にけふ、と気の抜けたような音を発してしまう。
少し恥ずかしくなって赤面してしまった私をあやすように、私の体を包み込むスライムがやわや輪と私の全身を揉み解していく。くすぐったくて、もどかしくて、でも何処か気持ちよくて……。
「んっ……んやぅ……♪」
手足の指と指の間や、脇、膝の裏といった場所を、まるでキスをするように吸い付いては離れていくスライム。吸い付かれたところから静電気を纏った服が吸い付くようなじんじんとした刺激が、そこを基点として私の中に広がっていく。しまりが悪くなっているのか、私の股間がまた潤み始めていく……。
「ふふ……♪」
それを察したのか、スライムマザーの手が私の股間に伸びていく。彼女の意思に合わせて、股間部分のスライムが左右に割り開かれて……すっかりぐじゅぐじゅになった私の秘所が顕になった。
「あ……んんっ♪」
恥ずかしくなって赤面する私に微笑みながら、マザーはなぞるように、膜を破らない程度に優しく、でもしっかりと肉の畝に触れていった。人間よりも何処か人間らしい瑞々しい手は、とろとろに濡れた私の秘所の肉をまるで労わるように擦る。きゅんとした心臓を高鳴らす刺激もそうだけれど、何よりも暖かさや、安心感が心の中に一杯浮かんでくる。
心地いい快感に身を浸しながら、私はスライムマザーの言葉を耳にしていた。
「アンリちゃん……この場所はね……とぉっても大切な場所なのよ……♪」
マザーの一言一言が、私の心の中に染み渡っていく。もっと聞いていたい、ずっと浸っていたい。もっと……もっと近くにいたい。今はマザーの中に居るお姉ちゃんが羨ましかった。きっとお姉ちゃんも、マザーにぎゅっとされて、同じことを考えたのかもしれない。
「ここはね……どんな辛い事も、悲しい事も、苦しい事も、優しく受け止めてあげることが出来る場所なの……♪受け止めて、受け入れて、分かち合って……そして思い出の一つとして小さく、見えないくらいに小さくしてあげられる素敵な場所……♪」
さわさわと触れられるたびに、私の中に明かりが灯るように優しい熱が発生していく。その熱は、少しずつ大きくなっていくのが分かる……。それがたまらなく嬉しくて……。
「メロディちゃんも、アンリちゃんも、ずっと辛い思いをしてきたんだって思うの。だからね……私は貴女達のママになって、それを、癒してあげたいんだ……♪」
ママになる、と話した時の、マザーの顔は、何処までも嬉しそうで……そして力強くて……。
きゅん、と私のお股が疼いた。もっと触れて欲しい、もっと、もっと繋がって欲しい……身体はそう求めている。マザーと、繋がりたい。それが身体の正直な思いだ。
「んんっ……♪」
スライムマザーの片手は、私の秘所をなぞり終えると、そのまま上へと持っていった。丁度、臍と股間の中間辺り……子宮のある辺りを擦りながら、もう片方の腕で私を抱き寄せていく。ふわり、と優しい香りが濃くなった気がした。
マザーに触れられているだけで、子宮や股間がきゅん、と切なく音を立てる。どうしようもなくふわふわで、どうしようもなくゆらゆらした私の今の精神。心臓はどくどくと高鳴りを続けている。くらくらしてしまいそうだ。
そんな心を一押しするように、スライムマザーは瞳を潤ませながら、私にゆっくりと語りかけていく。
「……ねぇ、アンリちゃん……私の娘に――きゃっ♪♪♪♪♪♪」
最後まで聞かなくても、私の心は決まっていた。スライムマザーの胸の中に飛び込んで、頬擦り。大きな胸に埋もれながら、私はマザーの香りをすんすんと体の中に吸い込んでいた。胸の中の香りは、他の場所に比べて濃縮されており、少し嗅いだだけで体中の力が抜けてしまう……。
「……あら……ふふふ♪」
……締りの悪い私のお股から、再びおしっこが漏れてしまい、スライム服の中に放ってしまって……ちょっと恥ずかしくなってしまった……。
「……ふふ……♪さぁ……いらっしゃい……アンリちゃん♪」
私の前で、スライムマザーが大きく股間を広げ、既にお姉ちゃんを呑み込んだ穴を大きく見せ付けてきた。人の秘所と、その奥へと招く膣道を模したような形状のそれは、お姉ちゃんが通っていった筈なのに、傷の一つすら見当たらない。やわやわと震え、時折脈にあわせるように膨張し収縮しを繰り返すそれは、マザーの纏うスライムと同じ色をしているはずなのに、不気味さやグロテスクさよりも何処か、命の輝きや温もりが感じられた。
「帰っておいで……♪アンリちゃん……私の娘……♪」
まるで呼吸するかのように伸びたり縮んだりを繰り返す、彼女の神域へと至る粘体の洞窟。スライムマザーの声はその中から響いているようだった。その声に誘われるように、私は足をその中にやや潜り込ませつつ、彼女の顔を眺めていた。
「んっ……♪ぁああ……♪アンリちゃん……アンリちゃん♪」
とても嬉しそうに私の名前を呼びながら、スライムマザーは身体の洞窟を蠕動させ、私を奥へ奥へと招きこんでいく。ぬるぬるとした、温もりを持った粘体は生まれたままの姿となった私の身体に隈なく蕩けるような口付けと蕩かすような愛撫を行い、私の心をさらにぐじゅぐじゅにしていく。自分は何でこうしているのとか、魔物にいいようにされていていいのとか、そんなことを考える事すら、いや、考えるという行為そのものすら考え付かなくなる程に、私の心を融かしていく……。
ずぶり……ずうぶり……。やわやわと私の全身を包み込むスライムの肉は、私の体をどんどんその中へと埋め込んで沈み込ませていくようだった。それだけじゃない。私の形にぴったりと添うように、洞窟は形を変化させていく。苦しくなく、寒くも暑くもなく、心地よさが支配する空間へと、私は飲み込まれていく……。
「(んぁ……ん)」
私の体を包み込んだマザーの身体は、全身に細やかな愛撫を行ないつつ、私の体に密着していく。ぬるぬるとした触感に、ぺとぺとと吸い付く肉。境界が分からなくなるのも時間の問題だろう。
「(……あ……)」
スライムマザーの中に完全に呑み込まれる前に、最後に思ったことは。
「(……キス、したかったな……ありがとうの、キス)」
もっと、彼女に甘えたかったという、欲張りな願いだった。
――――――
――ぐぷ……ん。
「……んぁぁ……♪」
アンリとメロディ、二人を受け入れ終えたスライムマザーの身体、いや腹部は大きく膨れ上がり、まるで巨石を詰め込んだかと思われるほどの大きさとなっていた。立ち上がることも出来ず、ぺとりと乙女座りをしたマザーは、しかし何処までも幸せそうな表情を浮かべていた。さすり、さすりと、二人を『受け入れた』お腹を擦る彼女の、その視線の先。腹部にある巨大なコアがふるふると震え始める。
コアの周りに隆起している血管を思わせる管が、コアの中に何かを送り込むと、コアはそのまま一瞬膨張し……そのまま一気に収縮した。ぐじゅ、ぐにゅ、しゅる、ぢゅる。彼女の中で何かが生え、それが蠢くような音が響く。音が響く度に、スライムマザーは幽かな吐息と共に喘いでいく。
……くちゅ、ちゅぐっ。
「――んんんっ♪♪♪」
何かが密着する音が、二回。それと同時にスライムマザーは大きくその背を反らし、身体を走る快感に身悶えさせていた。
暫くすると、腹から聞こえる脈が大きくなる。コアやそれに繋がる血管のようなものが膨張と収縮を繰り返し、中に入る者へと栄養などを送り込んでいるらしい。その脈が、スライムマザーの脈とも合わさって、ハーモニーを奏でているようだ。
さす……さす……。スライムマザーは、自らの肥大化した腹を撫でながら、子守唄を唄うように、中にいる『娘』達に向けて語りかけていった。

「ふふ……♪元気に……生まれておいで……♪」
――――――
「(……ぁー……)」
……いつから、私はこうしているんだろう。目覚めるか目覚めないかの境目で、ただじっと丸まって……。
ぼんやり、ゆらゆら、ふわふわ。何も考えないで、何も考えられないまま、ただ揺られ、包まれ、抱き留められ……。
ピントの合わない目に映るのは、まるで水の中から空を見たような、ゆらゆらと光が揺れる水色。それが離れたり、逆にぴっとり、ぎゅうっと近付いたり……。隙間も、体の境目もわからなくなっていって……。
「(……ん、……ん……♪)」
お腹の中から、とくん、と音を立てて、暖かくて甘い何かが流れてくる……。とくん、とくとく、とくんっ……体が、じんじんする……あったかくて……甘くて……。
……あ、さわさわされてる……♪さわさわ……もっとさわさわして……♪
とくとく……さわさわ……とくとく……さわさわぁ……♪
「(……んぁ……?)」
……あ。私の向こう側に、同じようにママと繋がっている子がいる……。
あの子は……あれ?えっと……私が大切で、守らなきゃって思っていた気がする……。
だって……心細そうにふるふる震えて……私の影に隠れていて……。
「(……♪)」
……分かった♪私の妹だ♪
「(……んー……♪)」
ふふ……お姉ちゃんが、貴女のことを守ってあげるからね……♪
だから……安心して♪
……おうたがきこえる♪
ママ……私のママのおうただ♪
あ♪またなでなでしてくれた♪
うれしい♪
きもちよくて……あったかくて……うれしくて……やさしくて……♪
……あふぁ……。
ねむく、なってきちゃった……。
ママ……♪
妹……♪
……おやすみなさぁい……♪
――――――
姉妹がスライムマザーに呑まれて数日後。何処か晴れやかになった外の光が入り込むことの無い地底湖の辺にて、スライムマザーは飲み込んだときよりも心なしか大きくなったお腹を両腕で抱えつつ、静かに寝息を立てていた。時折もこり、もごりと隆起するお腹がもたらす刺激に「んっ……♪」と喜び悶えつつ、眠りながらもその両腕は体内の二人の位置を捉え、彼女達に届くように擦っている。
「ん……ふぁぁ……♪」
本日何度目かの腹部隆起を経て、ようやく目を覚ましたスライムマザーは、眠っていたときとはリズムを変えて、お腹の辺りを押さえ込むように擦り始める。それに喜んでいるかのように、右手の方のお腹がぼこぼこと隆起が激しくなる。
「んぁぁ♪アンリちゃんは元気一杯ね……♪メロディちゃんは……とってもお淑やかね〜……♪」
一方の左腕の方のお腹は、何処かためらいがちに膨れ上がったりするだけであった。記憶はまだ戻っていないはずなのに、既に現れている姉妹の……娘達の性格の違いに、何処か困ったような、でも何処か嬉しそうな表情を浮かべるスライムマザーは、お腹越しに二人を抱き締めるように、両腕でぎゅーっ、とお腹を抱き締めた。
「っんんんんんんんんんんんんっ♪」
二人とも驚いたようにお腹のあちらこちらを自由自在に変形させていく、その刺激のあまり、スライムマザーはくぐもった喘ぎ声を漏らしながら背を反らしてしまう。いつもならこの辺りで隆起は止まってしまうが……この日は止まる事がなかった!
「んん、んぁああっ♪ふふ……あぁん♪&そう……んんっ♪もうなのね……んんぁぁっ♪」
もこり、もこりといつになく激しく蠢くお腹をそのままに、スライムマザーは身体を横たえつつ、二人を呑みこんだ『口』を前にすると、スライムを使って口を大きく拡げ初めた!
「んぁふぅ……っ、出るときは……順番こに……ね♪」
右腹あたりから来る激しい突き上げに身悶えつつ、彼女はスライム独自のお産の呼吸を用いて自らの脈を整えていく。そんな親心を知ってか知らずか、左腹はおとなしく、右の娘が先に出るのを待っているようだった。
もこり、もごり。マザーの腹を押し広げつつ、右腹の子は押し広げられた出口へと元気よく迫っていき――!
「――んあぁぁぁぁぁああああああんんんっ♪♪♪」
――じゅぶぅぅぅぅぅぅっ……。スライムマザーの胎内を満たす羊水に近い成分の液体と共に、紅い粘液に覆われた一つのコアが転げ出て行った。それはすぐさま、周りの粘体を掻き集めて人間を思わせる形へと変化していく……!
「――んんんぅぅぅぁぁぁぁんんんんん……♪♪♪♪♪♪」
――ぼじゅっ……。紅いスライムが人の形をとり終わった辺りで、もう一つのコアがゆっくり、緑色の粘液を纏いながらころん、とマザーの中から転げ出て行った。それもまた、周りの粘液を集めて人を思わせる形へと変化していく……。
生まれ落ちた生まれ落ちた二匹のスライム……それは、マザーが身に収めた二人の面影を如実に残していた。紅いスライムの方がアンリで、緑色のスライムの方がメロディである。二人は自らの身体を作り上げると……変化したばかりでまだ使い慣れていない身体を何とか動かして、マザーの元へと近付いていった。
そんな二人の表情に……曇り一つ見られないことが感じられたマザーは、そのままスライムも使って二人を招き寄せた!
「わぁ!!」「きゃっ!!」二人が驚く間に、マザーは二人を胸元へと招き入れ……そのまま両腕を使って抱き締めた。母性のフェロモンがマザーから立ち昇ると、二人は驚いていた目をとろんとさせながら、マザーの顔を見る。
マザーは、そんな二人の額にキスをすると……心の底からそう思っている声で、優しく語りかけたのだった。

「生まれてきてくれて、ありがとう。ここが……貴女達の安らぎの場所よ♪」
――――――
――その後。
姉妹達との出会いを済ませた二人は、マザーの元ですくすくと成長していった。大きくなり記憶を取り戻したときにも、彼女らは戸惑い一つ見せず、その記憶を受け入れていたようだった。
姉となったアンリは、忠義のスライム騎士として各地で剣を振るい、妹のメロディは、人間だった頃にひそかに思いを寄せていたという男性と結ばれる事になるが……それはちょっとした、未来のお話。
Fin.
(All Illustrations are drawn and painted by kaname)
おまけ:メロディが囚われるまで
メロディが洞窟の奥にある地底湖に辿り付いた時、スライムマザーは自然を称え、平穏を称え、命を称えるスライム族に伝わる歌を優しい声で歌っていた。命の根源たる水を親として過ごすスライム族は、自然とは切っても切り離せない関係にある。そのため、娘達への教育も兼ねて、時を決めて歌声を響かせるのだ。メロディが子守唄のようだ、と感じたのも、あながち間違ってはいない。スライム娘達はこの歌と共に育っているのだから。
「〜〜♪……あら?」
いつものように唄い終えたスライムマザーが、普段聞きなれない音が響いた方向に眼を向けると、そこには瞳から涙をぽろぽろと零しながら、何処かうわ言のように何かを呟いている人間女性がこちらに向かっている姿があった。光が宿りつつも半端に濁ったその瞳……それだけで、スライムマザーの心は酷く苦しくなった。一体この人間の女性は何を経験したのだろう。何故こんなにも苦しんでいるのだろう、と。そして出来るなら、私が癒してあげたい、と。
きゅん、と腹部のコアが物欲しそうにねだる。どこかマザーは自分の腹部が波打っているようにすら感じられた。既に彼女の纏うスライムが彼女の周りで、でろりとその嵩を増していく。彼女自身も、目の前で涙を流す女性が愛しく感じ始めている。発情期、と表現してもおかしくはない状態に、既に身体の方は変化していたのだ。
「あ……ああ……!」
涙を流しながら、声にならない声で呻く女性――メロディに向けて、スライムマザーは腕を広げた。メロディの背をに回った彼女のスライムは、しかしメロディには触れず、まるで壁を作るように隆起していく。彼女の目に、マザーしか映らないようにしているのかもしれない。
ゆっくりと、お互いにその身体を近付けていく二人。既にマザーの胸からはスライムが取り外され、瑞々しい肌を顕にしていた。そのたわわに実った水桃の狭間に、メロディはその涙で濡れた顔を押し付けた。
「んっ……ぅ……♪」
ぽふん、と彼女を受け入れたマザーの胸は自在に姿を変え、うにゅむにゅとメロディの泣き声ごと顔を飲み込んでいく。涙が身体に染み入る独特の感覚と、両胸を刺激される気持ちよさにほんの少し吐息を漏らしつつも、マザーは己が今為すべき事を理解し、両腕を彼女の背中に回した。そして、優しく子供をあやすように、ゆっくりと彼女の頭をなで始めた。
「どうしたの……?そんなに悲しい事でもあったのかしら……?」
「う……ああ……あああ……!」
ぽふ、ぽむ。頭を優しく撫でられる度に、メロディの泣き声は大きくなり、涙の雫と共にマザーの身体を揺らしていく。涙の一粒一粒に詰まっているメロディの感情に反応しているのか、マザーコアがキュン、と物欲しそうな感情をマザーに伝えた。スライム達の壁も、ゆっくりとメロディの身体に迫っていく。
「いくらでも、泣いていいのよ……♪私は、貴女の悲しみをいくらでも受け止めるから……♪」
マザーの言葉には、魔力が篭っている。身体全体から漂う甘い香りと同様、人の心を融かし、素直にして、マザーのことを大切に思うようになる魔力が自然発生的に篭っているのだ。メロディの心は、その魔力に抗う事を知らない。故に、マザーの言葉を受けて……泣いた。激しく、もしも胸に埋まっていなかったら洞窟の中に声を響かせていたのではないかというくらい激しく、泣いた。
「……ぁぁぁぁぁぁぁぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ……!!!」
「……よしよし……いい子……いい子……♪」
涙が、感情が、余すところなくスライムマザーの中に叩き込まれていく。彼女がずっと抱えていた悲しみが、心のゴミのようなものをすべて押し流すかのような奔流となって、涙と共に外に排出されているかのようだ。その涙を、マザーは受け入れて、受け入れて、ただ受け入れ続けた。胸は相変わらずメロディを捕らえて離さず、コアはメロディを求めてマザーを急かし続けている。
声が枯れてしまうような勢いで激情を叩きつけ続けるメロディ。その声が小さくなり、やがてすすり泣きになり、それすらも小さくなって……その間、ずっと抱き締め続けていたマザーは、泣き疲れてしまったメロディの頭を、ゆっくりと、胸から解放した。先程まで変幻自在に形を変えていた胸は、すぐに張りのある姿を取り戻していく。
「ふふ……そんなに泣き叫んで、喉が痛くなったでしょう?おあがりなさい……♪」
泣き腫らした目で、歪んだ視界の先にメロディが見たものは、つん、と主張する隆起した乳首であった。その先端に、幽かにぷるぷると震える何かがある。言葉に促されるままに、メロディはそれを舌先で舐め取った。
「んんぅ♪」
舐め取ったものは……舌先からじんわりと、体の中に染み渡っていく。甘い。甘いだけじゃなくて、暖かくて、優しくて、身体だけじゃなくて心に染み渡っていくような錯覚すら覚えてしまう……。もっと欲しい、もっと口にしていたい。身体からの欲求に、メロディは純粋に従った。
ぺろり、ぺろり。
「んぅ、んんぁ♪」
初めは舌先で乳首の先端を舐めるだけであったメロディであったが、次第に埒があかないと感じるようになってきたのか、乳首を唇でつまむようになり、そのまま乳房に吸い付くようになった。
「んゃぁぁ♪んんっ♪んぁぁ……♪」
ぴゅるり、ぴゅるりと乳腺を通り母乳がメロディの中に入っていく。母乳というよりプルプルした感覚からゼリーやスライムという表現の方が正しいのかもしれないが、それをメロディはただただ、身体に促されるままに呑み続けていた。
「ふふ、可愛らしいわね……♪」
その様子を優しい眼差しで眺めながら、スライムマザーはゆっくりと服を脱がせていく。服のつなぎ目だけを器用に融かして、また縫って着せられるように綺麗に畳める布地にしながら、メロディを生まれたままの姿にして……絶句した。
「!?」
メロディが身に纏っていた長袖の下、そこには顔をしかめたくなるほどの『暴行』の痕が見て取れた。無数の痣、裂傷、火傷、魔法生物による被害、そして『肉便器メロディ:無料』などと記され――いや、刺青され、黒く染まるまで使い込まれた秘所など、その凄惨さから常人なら吐き気を催しかねない有様が見て取れた。人間に憎しみを覚える事のなかったスライムマザーでも、この仕打ちを彼女に与えた存在に対し強い憤りを覚えさせてしまうほどの惨たらしい有様、これがメロディの心の中に巣食うゴミであることを、マザーは痛感し、そして決意させた。
「……メロディちゃん?」
「……?」
乳をこくこくと飲みながら、上目遣いで眺めるメロディ。その濁りの中に一点の光が見える瞳を見つめながら、何処か自分に言い聞かせるような口調で、マザーは呟いた。
その瞳に、我が子を思いやる慈愛の涙を浮かべながら。
「……本当に、辛かったんだね……苦しかったんだね……!」
ぽたり、ぽたりと、スライム状の涙が彼女の肌を伝っていく。癒しの魔力が篭っているのか、傷跡に接触すると、その痕が薄まっていくのが見て取れる。じわり、と体内に染み込む熱に驚いたのか、メロディは飲みかけのスライムを口の端からたらりと零しながら、乳首から口を離してしまう。
「……忘れられないのよね……忘れたくても、体が思い出してしまうのよね……!」
ぎゅっ、と、マザーの両腕はメロディの身体を包み込みように抱き締めた。招く先は自身の胸の中だ。
「――はぷっ!」
メロディが驚いたのもつかの間、すぐに身体から溢れる甘い香りと沈み込む胸の感触によって意識に靄がかかっていく。先程までよりもさらに力が篭った抱擁によって、二人の肌はさらに触れ合い、マザーから放出される魔力の影響もさらに大きくなる。
「――ふぁぁ……」
既にとろとろに蕩けつつあるメロディの心だが、スライムマザーはそれだけではいけない、と感じていた。あくまでも、今は心を融かしただけで、メロディを癒せたわけではない、と。遠い思い出にしてしまうことは出来るけれど、それではあまりにもメロディが可哀想だ……。
「……メロディちゃんの経験を、思い出になんかさせない……!」
マザーは、強い決意と共に慈母の表情を浮かべ、幽かに抱く力を弱めつつ、メロディに向けて呟いた。
「……私が、メロディちゃんのその傷跡を、消してあげる……!思いださなくてもいいように……優しい笑顔に戻れるように……!」
メロディが、自身の身体に違和感を覚えたのは、その声と同時であった。
「ひぅっ!?」
嫌悪感、というには鋭い刺激が、彼女の予測もつかないところから発生した。それは発生地点から脊髄を昇って脳へと一瞬で到達し、何をされているのかを脳が情報として理解するよりも早く、刺激がもたらす快感をメロディの全身に伝達した!
自分の身体に何が起こっているのかわからないまま、メロディはマザーの体に身を押し付けたままがくがくと震わせる。マザーはそんな彼女の体を、下からじわりじわりとスライムで覆い始めていく。
「――ひゃぁぁぁっ!!!」
再び、メロディの身体――お腹の辺りに刺激が走り、瞳を大きく見開いてびくびくと身体を振動させる。今度は理解できたようだ。彼女の体の中で、何かが彼女の体を舐め擽り、そして浸透してきているということに!
ぺろり、ぺろり。身体の内側を舐められているという普通ありえない、あるはずのない事態にメロディの身体はただ喘ぎ声を発する生きたバイブとなったかの如く、その震えを収めることがない。いや、収めることが出来ない。舐められている箇所が増える度に、そこからジンジンとした熱が発生し、より彼女の体を敏感にしていくのだ。
「――ひぁんむうぅぅぅぅ……!」
その口を塞ぐように、マザーは乳首を挿しこみ乳房で隙間を覆い、そのまま再び母乳もとい母スライムを飲ませ始めた。条件反射的にこくこくとメロディは飲み干してしまうが、それが舐められた跡を通過する度に、何処かもどかしいようなこそばゆいような刺激が走り、顔を赤らめながら悶えてしまう。眦から伝う雫が持つ熱は、間違いなく今、メロディが受けている刺激で体が火照っている証でもあった。
刺激は中だけではない。彼女を包み込んでいくスライム達もまた、彼女の受けたあらゆる傷に触れ、癒していく。その過程で生じる熱が、彼女の体を昂ぶらせていく。それに対して、メロディは恐怖感を抱く様子はない。いつぞや味わったという“悪夢”のフラッシュバックは起こらず、ただ安寧の中で刺激に翻弄されているだけだ。
「……」
だが、メロディの身体を『浄化』しているマザーの顔は、何処までも憂いに満ちている。未だメロディの身体を汚す物の残滓が、スライムから『苦味』として伝達されているのだ。マザーに薬物の知識はない。無いけれども、未だメロディの中に残るこの物質たちが毒物であり、用いた人物が相当の悪意と独善のためにこれらを彼女に投与した事を感づくのは容易ではあった。そして、これを消さない限り、メロディが真に笑顔になっる事も無いという事も、また。
「うむぅぅぅぅ!んうんんんっ!」
じわり、じわりと傷跡から広がっていく熱と快感、その先にあるそこはかとない心地よさに、メロディの眦から涙が溢れていく。その間にもマザーの乳からはスライムが溢れ体の中を満たし洗い、彼女の皮膚をマザーのスライムが首から下を覆い洗っていく。傷跡も、落書きも、全てが元から存在などしていなかったかのように消えていく。高鳴る心臓はあちらこちらから吸収されたスライムの魔力を全身へと運び、身体の力を抜き、心を安らげていく……。
マザーは、そのメロディに吸収された彼女の魔力を、徐々に彼女の子宮に集めていった。同時に、ただ覆うだけだった秘所のスライムを、少しずつ彼女の胎内に潜り込ませていく。
「――!!!!!!!!??????????」
ずたずたにされた痛々しい膣内を、スライムは優しく覆い、そしてじわりと浸透させていく。まるで膣が独立した意思を持ったようにきゅんと締まり、スライムをもっと欲しがっているようだった。
それに応えてひくひくと疼く肉襞を覆い尽くしたスライムは、そのまま彼女の奥――生命の神が宿る神域、その入り口の子宮口まで辿り付くと、開いたままのその入り口に、その身を潜らせ始めた。
「!!ん!!!んん!!!!」
“満たされていく”感覚に声にならない声を漏らすメロディ。すぐさま新たな熱が生まれ、彼女を昂めていく。まるで彼女の体全てがスライムという皮膚に包まれた熱を血液とする心臓になってしまったかのように、体の中を荒れ狂う熱に彼女は翻弄されていく……!
じくじくと傷んでいたはずの傷口が、完全に塞がった事を確認したマザーは――。
「いたいの、いたいの、とんでいけ〜……♪」
――その声と共に、メロディの身体の至るところを、スライムを用いて優しく、撫でた。
「――んぁ、ぁぁああ〜〜〜〜っ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」
――ぷしゃぁぁぁぁぁぁぁ……
……思わず乳から顔を離し叫ぶほどの絶頂と共に、メロディの身体の中からありとあらゆる“悪夢の痕跡”が外にひりだされていく。じんじんと火照った秘所に塗りたくられ射ち込まれた薬の痕跡も、幾度となく飲まされた謎の液体も、尻を裂いた道具の感触も、みんな……『浄化』したスライムと共に排出され、マザーのスライムが全て“受け入れ”た。
「……ぁー……♪」
もう、全身を弛緩させ、絶頂の余韻に浸っているメロディの身体に、あの悪夢は存在しなかった。そして心の中からも、すぐに存在しなくなることは明白であった。
じゅるり、と音を立てて、スライムに包まれたメロディの体が、足からマザーの秘所の中に滑り込んでいく。包まれた場所から魔力が注ぎ込まれていく感覚に、メロディの瞳がさらにとろんとしていく……。
「ふふ、ゆっくり……お休みなさい♪辛い事も悲しい事も、全部ママの中に吐き出しちゃっていいのよ♪」
どくん……どくん……。ふるふると震えるマザーの身体の中で、コアが脈打ち、スライム肉の壁を揺らしていく。その度に、ずぶり、ずぶりとメロディの身体はマザーの中へと収まっていく。柔らかく全身を包み込むスライムは、まるで洗い立ての毛布のようで、暖かく、そして優しかった。
「……?」
胸元までマザーに飲み込まれた彼女の瞳に、自分と似た人間の姿が映る。思い出す力は彼女にはもう無かったが、何処か懐かしいような、嬉しいような、そんな感情が浮かんできて……。
「……♪」
彼女の意識は、そこで途切れた。
fin.
書庫へ戻る